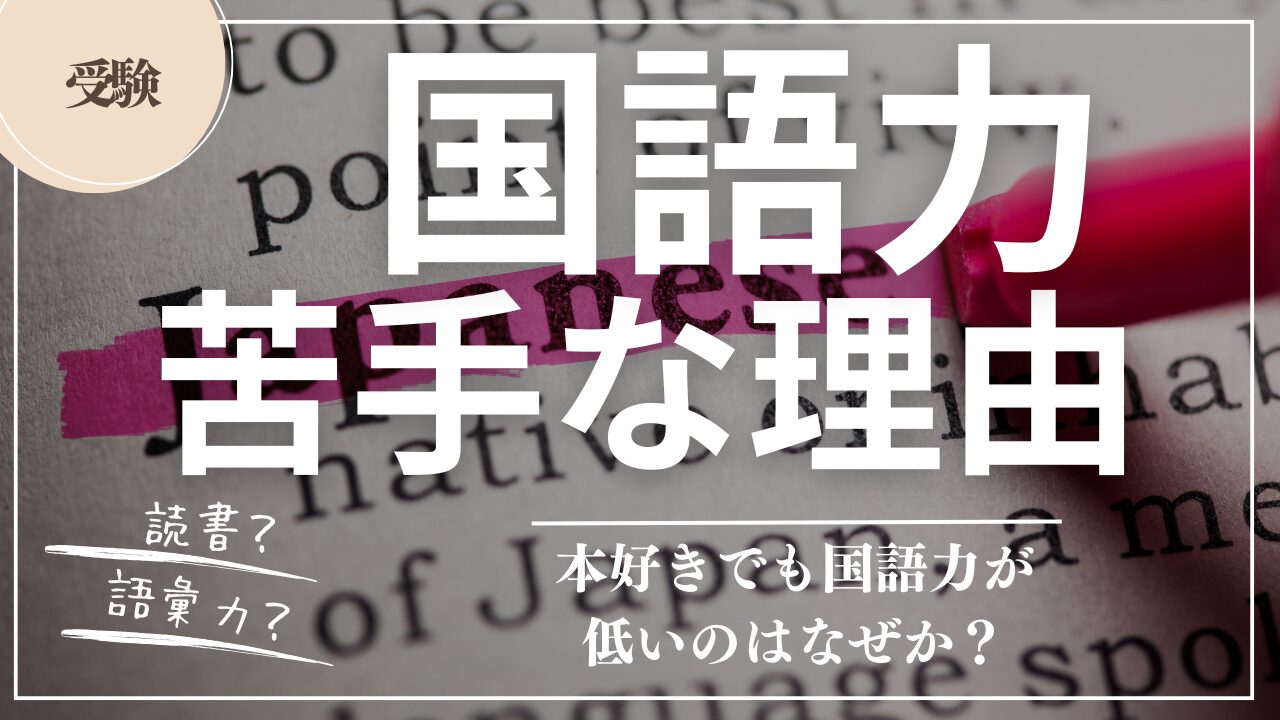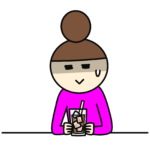
うちの子の国語の成績がなかなか上がらなくて・・・。
読書が嫌いなわけじゃないんだけど・・・。
なぜなのかさっぱりわからない。

最近は国語力が下がっているというのもニュースになっていたね。
「ごんぎつね」の解釈がしっかりできなくて、小学校の先生も頭を抱えているとか・・・。

今回は、国語力が低下してきている原因と、対策をまとめてみたので、受験勉強に悩んでいる親御さんやお子さんに読んでもらえると嬉しいな。
はじめに
「読書が好きなのに、国語の点数が伸びない…」
そんな不思議な悩みを抱える子どもは少なくありません。
多くの人は「本好き=国語が得意」というイメージを持っていますが、実際にはそうとは限りません。読書量が多くても、模試や定期テストで点数が思うように伸びないケースは多々あります。
この記事では、
- 本好きなのに国語が苦手な理由
- 語彙力が伸びない原因と背景
- 国語力を上げるための具体的な受験対策
- 近年の学生の国語力低下についての考察
を詳しく解説します。
特に保護者や受験生に役立つ、実践できるトレーニング法も紹介します。
◻︎受験勉強を頑張っている親子
◻︎国語の成績が伸びなくて悩んでいる子
◻︎国語の力を伸ばすにはどうしたらいいかを知りたい人
◻︎読書のやり方を知りたい人
◻︎本は好きなのに国語の成績が上がらない人
◻︎最近の学生の国語力の低下が気になる人
本好きなのに国語が苦手な理由とは?
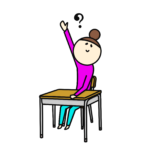
国語力を上げるには、読書をするといいと聞いたんですが、本を読むだけじゃダメなんですか?
読む「量」だけでは不十分
読書が好きな子は確かに文章に触れる時間が多いですが、読む本のジャンルが偏っていることが少なくありません。
たとえば、ファンタジー小説や推理小説など、物語中心の作品ばかりを読んでいると、描写や会話の表現には強くなりますが、論説文や説明文の読解力は鍛えられません。
試験では物語文だけでなく、評論や古文漢文も出題されるため、「幅広く読む」ことが不可欠です。
物語読解と試験読解の違い
趣味の読書は「楽しむため」に読むものですが、国語の試験では「筆者の意図を正確に読み取る」「根拠を示して答える」力が必要です。
例えば物語で「この登場人物はなぜ怒ったのか?」を答えるとき、試験では本文中の根拠を引用することが求められます。
しかし趣味の読書では、なんとなく感覚で理解し、根拠を意識する習慣がありません。
この「感覚読み」と「論理読み」のギャップが、国語の点数に影響します。

引用か!
確かに、読書する時って、サクッと流しちゃってることが多いわ!
知らない言葉を飛ばしてしまう癖
物語は多少わからない言葉があっても、全体のストーリーは理解できてしまいます。
しかし、この「わからないまま読み進める」習慣が、語彙力の伸びを妨げます。
例えば「悠然と歩く」という表現を「なんとなくゆっくり歩くことかな?」と感覚で済ませると、本来の意味「落ち着いてゆったりと歩く」が正確に定着しません。

気になった言葉や漢字は、ちゃんと意味を調べる必要がありそうだね。
語彙力が上がらない原因とその背景
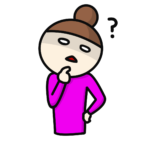
本を読んでいるはずなんだけど、説明とかは全く意味不明で文章になってなかったりするのよね。
辞書や検索を活用しない
語彙力は「知る→理解する→使う」というステップで伸びますが、多くの子どもは「知る」段階で止まっています。
わからない言葉が出ても辞書を引かず、なんとなくの理解で読み進めてしまうのです。
電子辞書やスマホ検索で簡単に調べられる時代ですが、「調べる習慣」そのものが身についていないことが問題です。

知ったらちゃんと理解して、日常生活で使ってみると定着しやすいよね!
日常会話での使用機会不足
せっかく本で新しい言葉を知っても、会話や作文で使わなければ忘れてしまいます。
語彙は「使える形」で定着してこそ、本当の力になります。
例えば「慎重」という言葉を本で知ったら、日常会話で「もっと慎重に進めよう」などと使うことで、記憶に残りやすくなります。
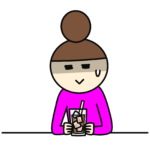
親子の会話も国語力に影響があるのね・・・。
ネット・SNSによる文章環境の変化
LINEやSNSでのやりとりは短文・省略形が多く、複雑な文章をじっくり読む機会が減っています。
その結果、文章構造を把握する力や語彙の幅が広がりにくくなっています。
さらに、ネット記事は見出しだけ読んで内容を飛ばす「流し読み」が習慣化し、深い読解力が育ちにくい傾向があります。
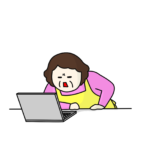
SNSをみていると、短く簡単に書かれているからなんとなくわかった気になるのよね!でも、長文の問題とか出てくると途端に拒否反応が出ちゃうかも。
国語力を上げるための受験対策
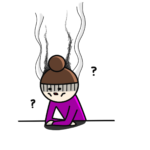
じゃあ、どうやったら国語力が上がるのかしら?
ジャンルを広げた読書
小説だけでなく、エッセイ、評論、新聞記事、歴史書、科学解説本など多様な文章に触れることで、試験に出やすい語彙や論理構造を自然に吸収できます。
おすすめジャンル例
- 論説文:池上彰の時事解説本、NHK「100分de名著」シリーズ
- 説明文:子ども向け科学雑誌『Newtonライト』
- 古典:マンガで読む古典文学シリーズ
要約トレーニング
文章を100〜200字でまとめる練習は、内容把握力を高めます。
新聞の社説やコラムを短く要約する、読んだ本の感想を一文で書くなど、日常的に取り入れられます。
コツ
- 誰が何を主張しているのかを押さえる
- 根拠や理由を省かずに盛り込む
- 自分の意見は入れない(まずは客観的に)
語彙ノート作り
新しい言葉を見つけたら、意味・例文・同義語・反対語をまとめます。
さらに、週に1回はその中から5語を選んで作文や会話に使うことで、「知っている語彙」が「使える語彙」に変わります。
近年の学生の国語力低下の背景
読書時間の減少
全国学校図書館協議会の調査では、1日の読書時間が0分という小中高生が増加傾向にあります。
スマホ・ゲーム・動画視聴が、読書時間を大きく圧迫しています。
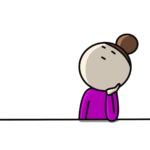
ゲームやって動画見てって、時間がいくらあっても足りないもんね。
読書に時間を使う若者は少なくなるわけだ。
長文読解の経験不足
SNSの短文文化に慣れた世代は、複雑な文章構造や長い説明文を読む集中力が低下しています。
そのため、入試問題のような長文を読み切る持久力が不足しがちです。

動画視聴も倍速で見る若者が増えたよね。
じっくり一つのことに取り組む力が低くなっているのかも。
授業の変化
授業時間の制約や学習指導要領の変更により、深い読解よりもテスト対策中心の授業が増えています。
これにより「文章を楽しむ力」「自分の言葉で表現する力」が弱まり、国語全体の力が落ちる傾向があります。

成績を上げるよりも前に、国語の楽しさや表現の美しさを感じることが大事よね!本来、読書って楽しいものなんだから。
国語力アップにつながる!小学生・中学生におすすめの本リスト

国語が苦手でも読みやすく、かつ語彙や読解力が伸びる本を厳選したよ!
「物語」「説明文」「古典・歴史」の3ジャンルに分けています。
小学生向け(低学年〜高学年)
1. 物語系(読みやすく感情理解力がつく)
- 『西の魔女が死んだ』(梨木香歩)
心の機微を丁寧に描き、情景描写が美しい。文章読解の基礎が身につきます。 - 『ふたりはともだち』(アーノルド・ローベル)
短編形式で読みやすく、会話や状況描写から登場人物の心を読み取る力が育ちます。 - 『チョコレート戦争』(大石真)
推理要素があり、論理的な展開の追い方を学べます。
2. 説明文系(知識+読解)
- 『科学のアルバム』シリーズ(あかね書房)
写真と解説文で構成され、説明文読解の練習になります。 - 『ざんねんないきもの事典』(高橋書店)
ユーモラスな文章ながらも語彙が豊富で、知識の幅も広がります。
3. 古典・歴史入門
- 『マンガで読む古事記』
古典世界観への入り口として最適。 - 『まんが日本の歴史』(小学館)
歴史の流れを理解することは論理的読解にもつながります。
中学生向け(基礎+応用)
1. 物語系(深いテーマ性)
- 『銀河鉄道の夜』(宮沢賢治)
抽象的な表現や比喩に触れ、解釈力を鍛えられます。 - 『坊っちゃん』(夏目漱石)
明治期の文章に慣れつつ、風刺やユーモアを読み取る力を養います。 - 『博士の愛した数式』(小川洋子)
論理性と感情表現が両立した文章で、幅広い読解力を伸ばせます。
2. 説明文・論説文系
- 『池上彰のやさしい日本経済』(講談社)
時事問題に触れながら、難しいテーマを読み解く練習に。 - 『10代からの批判的思考』(PHP研究所)
情報を整理し、根拠をもって考える習慣が身につきます。
3. 古典・歴史系
- 『平家物語(現代語訳付き)』
リズム感のある文章で古典への抵抗感を減らします。 - 『ビジュアル日本の歴史』(講談社)
図解+文章で時代背景の理解が深まり、歴史文章読解に強くなります。
読書の取り入れ方ポイント
- 「好きなジャンル」と「苦手なジャンル」を交互に読む
- 読んだ後に「一文要約」や「感想メモ」を書く
- 家族や友達と本の内容について話す
これらを意識するだけで、ただの「読書好き」から「国語も得意」な子へと成長できます。
まとめ
本好きなのに国語が苦手な子どもは、読むジャンルの偏りや、語彙を定着させる習慣不足、試験型読解力の不足が原因であることが多いです。
しかし、ジャンルを広げた読書・要約練習・語彙ノートなどを意識的に取り入れれば、確実に国語力は伸びます。
読書はあくまで土台。そこに「調べる」「使う」「論理的に読む」という意識を加えることで、受験でも社会でも通用する国語力が身につきます。