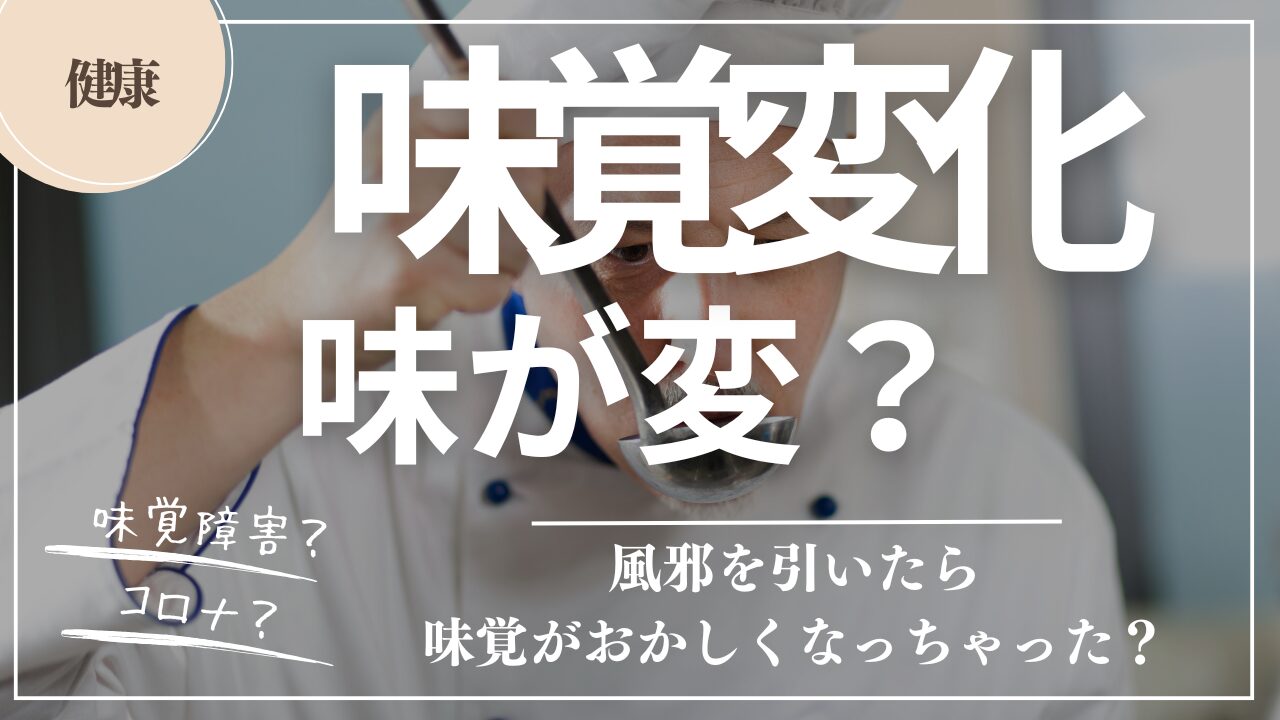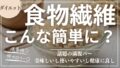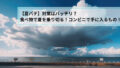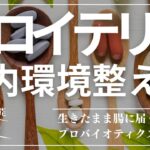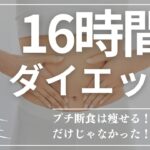〜子どもの味覚変化と親が知っておきたい対応〜

子供が風邪ひいてから、舌が不味くなったていうか、あんまり食べ物が美味しく感じないらしいの・・・。

風邪によって味覚に変化が出ているのかもしれないね!
じゃあ、今回は、なんで風邪を引くと味覚が変になるのかに注目してみよう!
風邪を引くと味覚が敏感になるのは、なぜか?
風邪で鼻が詰まると「においの情報」が変わる
風邪を引くと、鼻の奥が炎症を起こし、においを感じる神経が鈍くなります。
本来、人は食べ物の「味」を舌だけでなく、鼻からの香りの情報と組み合わせて感じています。
試しに鼻をつまんでご飯を食べてみるといいでしょう。
いつものおいしさが感じなかったり、全く味がしないなんて場合もあります。
それくらい、食べ物において嗅覚というのが重要な役割を担っているのです。
つまり、鼻が詰まってにおいが届かないと、「味そのもの」が変化して感じられます。
結果として、「苦い」「酸っぱい」「しょっぱい」といった一部の味覚だけが強調され、敏感になったように感じるのです。
免疫反応による一時的な味覚変化
風邪を引くと、体はウイルスと戦うために炎症反応を起こします。
このとき、舌の表面にある「味蕾(みらい)」という味を感じる細胞にも炎症が起きたり、代謝が乱れたりすることがあります。
すると、一時的に味覚が過敏になったり、逆に鈍くなったりするのです。
とくに子どもは大人より味蕾の数が多く、味覚が繊細。
そのため、風邪のときは「ごはんがまずい」「苦い」と感じやすくなります。
薬の影響も見逃せない
風邪薬や抗生物質の中には、味覚に影響する副作用をもつものがあります。
特に抗生物質の一部(マクロライド系など)は、金属的な苦味を感じやすくすることがあると言われています。
子どもが「薬を飲んだあと何を食べても変な味」と言う場合は、薬の成分が舌に残っている可能性もあります。
風邪の後に味覚障害を治す方法
味蕾を回復させる「ビタミンとミネラル」を意識
味覚の回復には、亜鉛・鉄・ビタミンB群などの栄養が欠かせません。
特に亜鉛は味蕾の再生を助ける重要な栄養素。
レバー・牡蠣・牛肉・卵・ナッツ類などを、風邪の回復期に少しずつ取り入れましょう。
ただし、食欲がない時期に無理をすると逆効果です。
まずはおかゆやスープに卵を加えるなど、消化の良い形で栄養をとるのがコツです。
口の中の乾燥を防ぐ
風邪を引いて口呼吸になっていると、舌の表面が乾き、味蕾がうまく働かなくなります。
加湿器を使う、こまめに水を飲む、飴をなめて唾液を出すなど、口内環境を整えることも味覚回復に役立ちます。
就寝中は、マスクを着用するのもおすすめです。
また、うがい薬や歯磨き粉の成分が刺激になることもあるため、風邪の間は低刺激タイプのケア用品に切り替えるのもおすすめです。
休養と睡眠で「神経の回復」を促す
味覚は舌だけでなく、神経と脳の連携で感じるもの。
風邪をこじらせて疲労がたまっていると、味覚神経の働きも鈍ります。
「早く治したい」と焦るより、しっかり休んで体全体の回復を優先することが、結果的に味覚障害の改善につながります。
風邪の時・味覚障害の時に食べられる食べ物
子どもにも食べやすい「やさしい味」
味覚が敏感になっているときは、塩味や酸味が強い料理がつらく感じます。
そんな時におすすめなのが、
- おかゆ(出汁や卵で風味を出す)
- にゅうめん(温かくて消化も良い)
- 野菜スープ(塩分控えめで香りをプラス)
特に出汁の香り(昆布・かつお)は、鼻づまりで鈍くなった嗅覚を優しく刺激してくれます。
苦味・金属味を感じやすいときは?
風邪や薬の影響で苦味を強く感じる場合、冷たい食事のほうが食べやすいことがあります。
たとえば、冷やした茶碗蒸しや、ポテトサラダ、冷製スープなど。
また、プラスチックや木のスプーンを使うと、金属味を軽減できることもあります。
大人におすすめの味覚回復レシピ
- 鶏むね肉のスープ:亜鉛・たんぱく質が摂れる
- 卵雑炊:胃にやさしく、栄養バランスも◎
- 果物(りんご・みかん):酸味で唾液を促す
味がぼんやりしても、「食感」「温度」「香り」で楽しめる工夫をすることが大切です。
コロナの時の味覚障害と、風邪の時の味覚障害の違い
原因の違い:嗅覚 vs 味覚そのもの
風邪の味覚変化は、多くの場合「鼻づまりによるにおいの遮断」が主な原因。
一方で新型コロナでは、ウイルスが嗅神経や味覚神経そのものに炎症を起こすことで、より直接的な障害を引き起こします。
つまり、風邪では「一時的な味の感じ方の変化」、
コロナでは「神経レベルの異常」が起きることが多いという違いがあります。
回復までの期間
風邪の場合は、通常1〜2週間ほどで味覚が戻ることが多いですが、
コロナの場合は数週間〜数か月かかるケースも珍しくありません。
特に味やにおいがまったく感じられない「無味無臭」の状態が長引くときは、耳鼻科への相談が必要です。
子どもの場合の見極め方
子どもが「味が変」「おいしくない」と訴える場合、風邪でもコロナでも共通して見られます。
目安として、
- 発熱・鼻水・咳がある → 風邪の可能性が高い
- においが全くしない/食欲が極端に落ちた → コロナや味覚障害の可能性
いずれにしても、2週間以上続く場合は受診を。
味覚の変化は、体からの大事なサインです。
風邪の時の味覚は「苦い?しょっぱい?」どんな変化が起こるのか
苦味を強く感じる
味蕾の炎症が起きると、苦味を感じる部分が先に過敏になります。
そのため、風邪のときに「何を食べても苦い」と感じる人が多いのです。
特に子どもは苦味に敏感なので、薬の服用後に食欲を失うことも。
塩味がきつく感じる
鼻が詰まって甘味を感じにくくなると、塩味だけが際立ってしまう傾向があります。
味噌汁やスープが「しょっぱい」と感じたら、出汁や香味野菜でうま味を補いましょう。
塩分を減らしてもおいしく食べられる工夫が、家族全員の健康にもつながります。
味がしない・変な味がする
風邪や服薬後に「何を食べても金属っぽい」「味が分からない」という症状が出ることもあります。
これは味蕾がダメージを受けているサイン。
放置すると慢性化することもあるため、症状が長引くときは耳鼻科で亜鉛の不足などを確認してもらうと安心です。
まとめ:行動と観察が「味覚を守る」
子どもの「味が変」「苦い」という言葉は、わがままではなく体調のサインかもしれません。
風邪による一時的な変化なら心配はいりませんが、
長引く場合や食欲低下が続く場合は、早めの受診を。
そして親としてできることは、
「食べなさい」と責めるのではなく、
味覚を回復させるための環境を整えること。
- 水分と加湿で口の中を守る
- 栄養と休息をしっかり取る
- 味覚を育てる“やさしい食事”を心がける
風邪が治るとき、味覚も一緒に元気を取り戻します。
その変化を見守りながら、親子で「食べる楽しさ」を取り戻していきましょう。